 |
|
伝承と伝統の民族文化遺産 |
 |
 |
祭りだ!神輿だ! 祭り神輿 |
 |
| |
 |
|
皇居外苑天皇即位20年祝賀パレード 平成21年11月 (不定期) |
 |
|
武蔵総社六所宮の大国魂神社旧御本社神輿の祭神大國魂大神は皇室の紋章と同じ十六菊を掲げる |
 |
|
皇居外苑天皇即位20年祝賀パレード
09.11.12.(木曜) 14:30〜16:30.
国民祭典 奉祝まつり
神輿パレード(皇居外苑馬場先門)
郷土芸能パレード(皇居外苑内堀通)
|
| 江戸消防記念会100名の木遣りの先導で神輿巡行開始 |
|
|
神輿巡行は荘厳に響き渡る鳶頭連の木遣りに先導されて、
日枝神社、神田神社、大国魂神社、十二社熊野神社を含む9基の神輿が巡行です。
皇居外苑馬場先門のお祭り広場を単純に二周して終了するというもので約2時間です。
前回は平成11年11月(1999年、即位十周年記念)に行われた。 |
|
日枝神社山車(九段四丁目の牛若と弁慶山車)昭和27年(1952)に浅草・宮本重義製作で太鼓の上に人形が乗る。
日枝神社神輿(駒札は山王であるが、八重洲一丁目東町会の檜物町神輿)明治43年建造。 |
|
 |
 |
|
|
九段四丁目の牛若と弁慶山車 |
台座三尺五寸の檜物町神輿 |
 |
 |
|
神田神社山車の獅子頭は破邪の霊獣として獅子を雌雄で山車に飾り付けて、行列を守護する。
関東大震災で消失したものを、やっと昭和58年に建造復活した。
極彩色の鳳凰を載せた神田大神輿は神田祭の陰祭りに瓔珞を付けて担がれる。平成12年の建造。 |
| 威圧する獅子頭山車 |
台座は四尺一寸の神田大神輿 |
|
|
|
宮神輿の大国魂神社と十二社熊野神社を先導する小足立八幡神社の太鼓と、恋ヶ窪熊野神社の御太鼓。
まるで曇り空を蹴散らすかのように太鼓が響き渡る。 |
|
 |
 |
|
|
小足立八幡神社太鼓 |
恋ヶ窪熊野神社の御太鼓 |
 |
 |
|
大國魂神社の昭和48年建造の台座四尺の御本社神輿のみは
幕で胴を覆い古式に則り烏帽子に白丁姿で担ぐ。
修正・参加したのは明治35年建造(平成15年修理)の旧御本社神輿です。
十二社熊野神社の台座三尺五寸二之宮神輿は平成9年建造でハードな千鳥担ぎを披露です。 |
| 大國魂神社の旧御本社神輿 |
十二社熊野神社二之宮神輿 |
|
|
|
江東天祖神社の獅子神輿2基は亀戸天祖神社の5年に1度の神明祭りは雌雄の大獅子頭の渡御。
神輿同好会の神粋会の万灯神輿 |
|
 |
 |
|
|
江東天祖神社獅子神輿 |
神粋会の万灯神輿 |
 |
 |
|
台座2尺5寸で屋根紋に十六菊を掲げる大拍子の太鼓と笛の大崎居木神社神輿と
茨城県下妻市の下妻囃子山車 |
| 太鼓と笛の大崎居木神社 |
殿の下妻囃子山車 |
|
|
|
パレード巡行順。(参加予定表より) 木遣(江戸消防記念会)、
日枝神社山車と日枝神社神輿、神田神社山車と神田神社神輿、
小足立八幡神社太鼓、恋ヶ淵熊野神社太鼓、大國魂神社神輿、十二社熊野神社神輿、
江東天祖神社獅子御輿、相模原神粋会万灯神輿、国分寺神輿会大鳥居神輿、高崎市粋心会神輿、
横浜市極神連合神輿、横浜市緑乃会神輿、川崎市道祖神神輿、居木神社神輿、茨城下妻囃子山車。 |
|
 |
|
郷土芸能パレード
皇居外苑内堀通り
14:30〜16:30.
参加団体は岩手県の江刺百鹿群舞、長野県の御諏訪太鼓、新潟県の新発田台輪、
愛知県の刈谷万燈祭、青森県の五所川原立佞武多等の13団体。 |
| 郷土芸能パレードは江刺百鹿大群舞で始まる |
|
|
岩手県の江刺百鹿群舞。
太鼓系鹿踊に属するもので主として、宮城県北部から岩手県南にかけての旧仙台藩領と、
旧南部藩領の一部に伝わる鹿踊です。
前腰に太鼓をつけ、背に一対のササラを立て、鹿角のついた頭(カシラ)をかぶり、馬の黒毛をザイとして用い、
頭から胸にかけて黒の幕垂れをさげ、自ら太鼓を叩き、歌を歌って踊るもので、
鹿踊は、お盆の頃には祖霊供養・悪魔追放のために、秋には五穀豊穣を祈願し踊られる。 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
飛騨高山祭りは春の山王祭りと、秋の八幡祭りの総称をいい、
春の山王祭りは12台の屋台が引き揃えられ、
秋の八幡祭りは11台の屋台が曳き揃えられます。
千葉東金囃子山車は、日吉神社で隔年(西暦偶数年)ごとの7月におこなわれる例大祭。 |
| 飛騨高山祭りは動く陽明門の屋台 |
神武天皇をのせた東金囃子山車 |
|
|
|
御諏訪太鼓は太古より農耕武勇の神として全国的な崇敬を集めて居る信濃の国一之宮諏訪大社の太々神楽を伝承し、
今から四百五十数年前、永禄4年9月、川中島合戦に於て、
武田信玄がこの太鼓で将兵の士気を鼓舞し有利な戦を展開したと伝えられる郷土芸能であり、
今日に息づく諏訪人の雄叫びである。 |
|
 |
 |
 |
|
新潟の城下町新発田の台輪。
戻る途中、少しでも前の台輪より先に出ようとする後車と、
そうはさせまえとする前車とのもみあいは意気と力を示すために、
あおりが幾度と無く繰り返される。あおる度に提灯の灯がゆれ、
金箔の台輪や見送り彫刻は、美しく華やかに揺れます。 |
| 勇ましい音頭取りの新発田台輪 |
金箔の台輪と見送り彫刻 |
|
|
祭りは、刈谷市銀座にある秋葉社の祭礼で、火難防除・町内安全を祈願する祭りです。
「万燈」は、高さ5メートル、重さ60キロの竹と和紙で作られた張子人形で、若者が一人で担ぎ、
笛と囃子に合わせて回転して舞う勇壮な祭りで、「天下の奇祭」と呼ばれている。
今回参加の張り子人形は源頼光の土蜘蛛退治、一の谷一騎打ち、鳴神の三つです。
写真は手前が土蜘蛛退治と一騎打ち。 |
|
 |
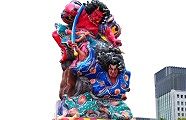 |
 |
 |
| この気迫この迫力 |
悠然と引かれるこれぞ立佞武多 |
巨大な夏祭りを彷彿させる |
五所川原市立佞武多(たちねぶた)祭は、青森ねぶた、弘前ねぷたと共に東北でも有数の夏祭りで、
古くは中国から伝わった「中元」の行事が起源といわれ、
400年以上もの間、津軽地方を中心に受け継がれて来た火祭りです。
この巨大ねぷたが、五所川原の記録に登場するのは、明治40年頃といわれています。
高さ約12間(約21メートル)のものが、数百人の若者によって担がれ、
町内を練り歩いたといわれています。
平成十年には電線が地中化され、高さ約22m(7階建てに相当)、重さ約17トンの巨大な山車が
「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」と練り歩き、
その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了しています。 |
|
|