 |
伝承と伝統の民族文化遺産 |
 |
 |
祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |
 |
| |
 |
|
亀戸香取神社神幸大祭 平成20年8月 (4年毎) |
神輿データ: 祭神:経津主神 台座:三尺九寸(117) 建造年度:明治11年(1879)
製作者:亀戸・錺師の矢澤 屋根と胴と鳥居が別々に揺れる別名こんにゃく神輿です。
|
|
 |
|
亀戸香取神社の魂ふりの都度「クイクイ」と左右に胴が振れるこんにゃく神輿 |
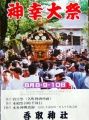 |
 |
 |
|
香取神社 例大祭 08.10.(日曜)
宮出し 6時半〜8時。
その後トラックにて大島に移動
明治通り大島より渡御開始
13時〜宮入 17時半
保存の江戸栄華300年前の古神輿
東京都江東区亀戸3-57-22。 |
| 大祭宮入ポスタ |
香取神社社殿 |
江戸の古神輿 |
|
|
香取神社創設は天智天皇4年(665)、藤原鎌足が東国下向の際、この亀の島に船を寄せ、
香取大神を勧請し太刀一振を納め、旅の安泰を祈ったのが始まりで江戸でも古社です。
天慶(938〜947)平将門が乱を起した時、追討使藤原秀郷はこの香取神社に参拝し戦勝を祈願したところ、
乱を平定することができ、神恩感謝の奉賽として弓矢を奉納し勝矢と命名。
この古事により、今も「勝矢祭」(5月5日)が守り伝えられている。
源頼朝、徳川家康などの武将達、また剣豪塚原ト伝、
千葉周作をはじめとする多くの武道家達の篤い崇敬を受け、香取大神を武道の祖神と崇め、
現在スポーツの神と慕われる。 |
|
 |
 |
| 明治通りを北進してくる宮神輿 |
宮神輿の引渡し場所での差し切り |
 |
 |
| 蔵前橋通りを渡御中も胴は微妙に左右に揺れ |
くいくいと黄金色の胴が微妙に左右に動く |
|
台座は三尺九寸(117CM) 建造年度は明治11年と古く 製作者は亀戸・
錺師の矢澤で明治11年に完成したもので、約5年の歳月をかけて製作された。
担ぐと屋根の部分・胴体の部分・台座の部分とそれぞれが別の動きをして、
俗称で「こんにゃく神輿」と言われ、
現在国内に2基(1基は九州)しか存在しない、珍しく貴重な神輿。まさにカラクリ神輿です。 |
|
 |
 |
 |
| 参道の香取大門商店街を |
第二鳥居前にて宮元に打ち止め |
本殿前で4年後約し宮入の木が入る |
蔵前橋通り第一鳥居から香取大門商店街は宮元が担ぎ、
第二鳥居から境内本殿前までは氏子役員が担ぐ決まりとか。
ご高齢たちで形だけ肩入れです。
宮入の木頭は存分担がせて、4年後にまた会おうぞと万感胸に木を入れる。 |
|
 |
|
「亀戸大根」 文久年間(1861〜64)
頃から栽培が始まり以来明治時代には香取神社周辺は産地の中心地となる。
肉質が緻密で白く冴えた肌の大根で根が30CM程度で先がクサビ状とがっていて、
おかめ大根・お多福大根と称され、早春に収穫されるため根も葉も浅漬けにして重宝がられたが、
大正末期には周辺の宅地化が進み、産地は江戸川区小岩や葛飾区高砂に移っていった。 |
| 香取大根発祥の記念碑 |
|
|
「亀戸」の地名 亀戸は昔小さな島からなっており、初め亀島または亀津島とも呼ばれ、
島の形が亀に似ているところから名付けられた。
現在、亀戸周辺には北に向島・牛島・南に大島、西に柳島など島にちなんだ地名が多く、
その昔、葦の海辺が次第に堆積して島となり、
村落を形成して漁村となり、これらの島々も四辺陸続きとなって、
亀島は亀村と称され耕地へと遷り変わってきた。
後に臥龍梅庭内にある亀ヶ井と混同され亀井戸と呼ぶようになったという説と、
亀津の津は戸の字義に同じであり亀津を亀戸といったとの説がある。 |
|
|