 |
|
伝承と伝統の民族文化遺産 |
 |
 |
祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |
 |
| |
 |
|
愛宕神社 出世の石段祭 平成19年9月 (隔年) |
神輿データ: 祭神:火産霊命 台座:六角一辺一尺五寸 建造年度:昭和56年 (1981)
製作者:石川輪島・神輿師 特記: 輪島塗屋根に三つ葉葵紋 珍しい六角神輿です |
|
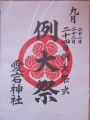 |
 |
|
海抜26mの愛宕山に鎮座する神社。慶長8年(1603)江戸幕府開府にあたり、
江戸の防火・防災の守り神として徳川の命により建立された。
正面の86段の男坂は講談で有名な曲垣平九郎が騎馬で上り、
馬の名手として世に名を馳せたことから「出世の石段」と呼ばれる。
江戸の頃より桜の名所としても知られる。
渡御日: 07.09.23. (定日) (隔年) 宮出し16時〜宮入19時半
東京都港区愛宕1-5-3。 |
|
愛宕山は標高26M。信じられないが東京23区内ではもっとも高い山です。
ここはNHKの発祥の地で第一声はここ愛宕山からはじまった。
日本で初めての生中継は大正14年岩木利夫(参謀本部馬丁)
が廃馬になる愛馬のために花道を作ろうと愛宕神社の石段を登った状況を中継したものです。
また全国各地に愛宕神社があるのは、江戸に出てきた諸藩が幕府に忠誠を誓う意味もあり
参勤交代の折りに江戸の愛宕の分霊を地元に持ち帰り小高い丘に「愛宕神社」を祀ったためです。 |
|
|
建造は昭和56年と比較的新しいが台座は六角一辺が一尺五寸で輪島塗屋根に三つ葉葵紋の珍しい六角神輿です。
細微にわたり手の込んだ彫金造りです。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
愛宕神社正面参道の石段は86段の急勾配です。
見下ろす恐怖心さえ芽生える石段を勇壮にも宮神輿が降りてくるのです。
そして祭り提灯の灯りを頼りにこの石段を登り宮入(還與)するのです。 |
 |
 |
 |
| 先導する町会神輿が石段降りの宮出しです |
続いて宮神輿が石段降りを始めました |
宮出し無事終えて氏子町内へ渡御です |
|
宮神輿も先導する町会神輿も急勾配の86段の石段での宮出し宮入を考慮して造られたのか
小型で軽量の神輿です。 |
|
 |
 |
 |
| 夕闇迫る中の宮神輿先導の渡御行列 |
背後の愛宕山から降りた鳥居前から渡御 |
ひと気がないビジネス街を宮神輿渡御 |
|
無事急勾配の石段降りの宮出し(発與・はつよ)を終えて氏子町内へと愛宕下通りを巡行して
行きます。勇壮な石段登りの宮入(還與)は19時30分です。 |
|
|