 |
文明開化の歴史的遺産 |
 |
 |
学び舎の時計塔/大学 |
 |
| |
 |
|
東京大学安田講堂の時計塔 |
|
東京大学安田講堂の高さ40mの時計塔。昭和34年安保闘争の全学連の拠点。昭和43年(1968)には
大学紛争攻防の火炎瓶と放水の応酬現場となるも、その時もこの時計塔は時を刻み続けた。
この安田講堂は安田財閥の初代安田善次郎の寄付によって建設され大正11年(1922)に建つ。
東京都文京区本郷7-3。有形文化財。撮影・05.02.09. |
|
|
|
設計者。 内田祥三。代表作・東大各文教施設、後に東大大学総長となる。 |
|
|
|
安保闘争。昭和34年からの(1959〜1960)日米安全保障改定に反対した大衆運動で
特に昭和35年6月全学連が国会突入した時に東大生の樺美智子が死亡したために
闘争は一挙に激化して岸信介首相は辞意、内閣も総辞職した。 |
|
| |
 |
|
東大駒場教養学部の時計塔 |
 |
 |
駒場東大教養学部1号館。明治11年(1878)駒場農学校として開校し本郷との敷地交換が行われ
旧第1高等学校となる。昭和8年(1933)に時計塔の1号館が本郷の安田講堂と同じ様式で建つ。
駒場公園や技術センターも同一敷地内であった。登録有形文化財。
東京都目黒区駒場3−8。撮影・05.11.19. |
| |
 |
|
東大駒場先端科学技術研究センターの時計塔 |
|
駒場東大先端科学技術研究センター13号館の時計塔。壁面の意匠が異なった4面の時計塔です。
旧東大航空研究所本館として昭和4年(1929)建築。
登録有形文化財。東京都目黒区駒場4-6。 |
 |
 |
 |
| |
 |
|
一橋大学付属図書館の時計塔 |
 |
|
シンプルであるが特徴ある時計塔の文字盤 |
 |
|
エントランス上部の中国の霊獣か怪獣か空想の猛獣なのか |
|
 |
 |
 |
|
国立の一橋大学西キャンパスの付属図書館の中国の霊獣か空想獣とロマネスク様式の時計塔。
右の写真は時計塔の右前にある国の有形文化財である同じくロマネスク様式のドッシリと構える兼松講堂。
建設は時計塔の付属図書館は昭和5年(1930)。兼松講堂は昭和2年(1927)である。 |
|
|
設計者。 伊藤忠太。代表作・東京築地本願寺、明治神宮、靖国神社、平安神宮等多数の神社仏閣がある。
日本画にも秀でていた。 |
|
|
ロマネスク様式。11〜12世紀の中世南フランス、西ヨーロッパの建築、彫刻、絵画の様式。
ゴシック様式に先立ち、教会建築を中心に古代ローマやゲルマンの諸要素を引き継ぐ。 |
|
 |
 |
 |
|
国立の一橋大学東キャンパスのロマネスク様式の有形文化財の東本館と2号館の時計塔。
静寂な武蔵野の雑木林の中にオシャレな時計塔が似合う。
東本館の設計者。伊藤忠太。建設昭和4年(1929) |
|
一橋大学。旧東京商科大学。異名「ピストル堤」の堤康次郎が昭和5年(1930)キャンパスを都内から国立に
移設を図った大学。その名残が時計塔の左側の昭和4年(1929)建築の東本館である。 |
|
| |
 |
|
慶応義塾図書館旧館時計塔 |
|
創設者福沢諭吉が明治4年(1871)に移設開校した三田の慶応義塾。
図書館旧館は創立50周年記念事業として明治45年(1912)竣工のラテン語の時計塔。重要文化財。
建物右側の最上階に八角塔が特徴的な赤レンガと花崗岩によるゴシック式西洋建物です。
時計文字盤はラテン語で「時は過ぎ行く」
「TEMPUS FUGIT」11文字が刻まれ12時には砂時計が彫られている。 |
|
|
設計者・曽禰達蔵。旧唐津藩士。代表作・東京海上ビル本館、日本郵船ビル、丸の内1〜7号館、
三井銀行小樽支店。 |
|
左側。慶応義塾の図書館旧館の正面とエントランス。
50周年記念と慶応義塾図書館が右書きで表示されている。
右側。昭和60年(1985)竣工の大学院校舎の時計塔。針は黒くシンプル。
共に港区三田2-15。撮影・05.10.14. |
|
| |
 |
|
早稲田大学大隈講堂の時計塔 |
|
創設者大隈重信が明治15年(1882)に開校した早稲田大学の
高さ38m4面の大隈講堂時計塔(東京都歴史的建造物)。
塔上の4つの鐘が今もウエストミンスター寺院と同じ
ハーモニーを奏で早稲田の町に時を告げている。建設は昭和2年(1927)です。
設計者。佐藤巧一(代表作・下記の大手町野村ビルに掲載)。東京都新宿区戸塚町1-104。
撮影・05.05.19. |
 |
 |
|
大隈重信。天保9年(1838)佐賀に生まれ、明治3年参議、明治21年(1888)と明治29年(1896)外務大臣を
歴任し、明治31年(1898)と大正3年(1914)大隈内閣をつくる。明治40年(1907)早稲田大学総長。 |
|
| |
 |
|
東京都立大学南大沢校舎の日時計塔 |
 |
 |
|
東京都立大学南大沢校舎の日時計塔。垂直の壁面2ヶ所に設置された殆ど目にすることない珍しい日時計です。
壁面右は5時から12時まで太陽顔が目を開く午前。左は12時から8時まで太陽顔が目を閉じる午後の日時計。
イニシャルの8の字は正午になると季節が変わっても
陰が8の字の何処かに重なる。撮影時間は03/21・11:56
目黒キャンパスから移転した平成3年(1991)の建設。
東京都八王子市南大沢1-1。 |
|
一橋大学西キャンパスの日時計。中央は台座の下にはめ込まれた
日時計の表示から修正して日本標準時にする均時差表。
右側の写真は日時計の台座に刻まれているのはスフインクスか
それともライオンでしょうか。または空想の怪獣だろうか。と
編集者はこの彫刻に魅せられた。撮影・05.05.21. |
 |
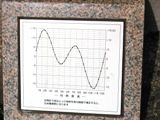 |
 |
|
日時計は最も原始的な時計で、紀元前3000年の古代エジプト文明ではすでに日時計学が扱われ
陰の長さや方向から太陽時を規定していた。機械式時計が普及し始める16世紀頃まで使用された。
ピラミッド、ストーンへイジなども時間を計るためのものとの説もあります。 |
|
| |
 |
|
東京農大の農学部本館時計塔 |
 |
 |
東京農工大学農学部本館の高くそびえる4面の時計塔。本館は昭和9年(1934)の建築で国の有形文化財に指定されている。
校内は松・ケヤキ・西洋杉等が生茂る25m前後の巨木の森林で包まれた武蔵野の大地です。
東京都府中市幸町3-5-8。撮影・05.11.01.
|
| |
 |
|
杏林大学医学部図書館の壁掛け時計 |
|
杏林大学医学部図書館のシンプルな大時計。敷地を囲むように校舎が建ち並び校内の中央にあるこの大時計は
外部からは殆ど目に付かない。偶然にも辛うじて南非常口から望めたのです。この大時計は
昭和54年(1979)に第4回医学部卒業生が記念として寄付されたものです。東京都三鷹市新川6丁目。 |
 |
 |
 |
| |
 |
|
立教大モリス館の時計塔 |
|
立教大学本館(モリス館)のツタが絡まった分銅式時計塔。文字盤は南北2ヶ所。
立教大は明治7年(1874)築地に開校するも大正7年(1918)池袋に移転。時計塔はその時建設された。
本館左側に図書館、右側に礼拝堂を配したゴシック様式で簡素かつ重厚な赤レンガ造りです。
東京都選定歴史的建造物。東京都豊島区西池袋3−34。撮影・05.08.30. |
|
| |
 |
|
武蔵野大学のガラスの時計塔 |
|
武蔵野大学のガラスの時計塔。ガラスで包まれた塔の中に文字盤を4面の時計塔。
大正13年(1924)浄土真宗築地本願寺内に「武蔵野女子学院」創立が母体。
昭和4年(1929)築地より緑豊かな武蔵野台地の現在地に移転。
「知・情・意」兼備の人間形成を目指す教育方針のままの時計塔です。西東京市新町。 |
|
 |
 |
| |
 |
|
錦城高校の時計塔 |
 |
 |
|
錦城高校の時計塔が武蔵野の大地に佇む。
静寂の緑地の中の整然とした学び舎を昭和38年建築の四面の時計塔が見渡しているようです。
東京都小平市大沼町2-633。
|
| 北正門から望む錦城高校の時計塔 |
中庭から時計塔を仰ぎ見る |
|
|
|
明治13年(1880)矢野龍渓によって東京三田の慶應義塾内に創立された「三田英学校」
が錦城高等学校の前身。
明治22年(1889)神田錦町に移転し「錦城学校」と改称。
昭和38年(1963)新たに現在地の小平に「錦城高等学校」を創設。 |
|
| |
 |
|
法政大学第二高等学校の時計塔 |
|
法政大学第二高等学校の白い三面時計塔。昭和14年(1939)男子校として開校。
昭和20年戦火に遭い校舎全焼。校舎は閑静は住宅街にあり白い時計塔校舎を中心に中学・高校。
時計塔の建設時期は不明だが昭和61年(1986)に第二中学校開校し現在は
中学校本館(時計塔)として使用している。
川崎市中原区木月大町6−1。 |
 |
 |
 |
| |
 |
|
ヤマザキ動物短大の時計塔 |
 |
 |
|
平成16年開校の東京八王子市南大沢のヤマザキ動物看護短大の時計塔。
母体は世界で初めてのイヌの美容専門学校として1967年に渋谷で開校。
最上階の木造建築による天井構造とステンドグラスのセントフランシスホールに隣接の搭上には鐘が付いているが鳴ることはない。
建物は簡素で、シンプルな建物です。
東京都八王子市南大沢4-7-2。 |
|