 |
|
伝承と伝統の民族文化遺産 |
 |
 |
祭りだ!神輿だ! 祭り神輿 |
 |
| |
 |
|
第二回 寒川神輿まつり 平成26年7月(毎年) |
 |
|
ドッコイどっこい!そいや〜と神輿揉み繰り返し御旅所に入る殿の八幡大神 |
| |
 |
|
第2回 さむかわ神輿まつり |
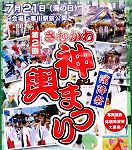 |
 |
 |
 |
| 寒川祭りPOP |
寒川駅前広場での式典 |
寒川神社の御旅所 |
平成9年建造総桧造りの寒川神社本殿 |
'14.07.21.(海の日) 寒川駅北口広場 式典 10:20 11:00神輿パレード 御旅所まで
浜降祭の伝統を守り継承し、祭りを通じて町を活性化し町民の皆さんを元気にしようと、
浜から引き上げてきた寒川の神輿が寒川駅前公園に集結し「さむかわ神輿まつり」を開催。
寒川地区の6社のうち、宮山の寒川神社、一之宮の八幡大神、倉見の倉見神社、岡田の菅谷神社が参加です。
式典では東日本復興祈願として寒川神社巫女の舞いも披露され、
寒川駅前公園から町商工会館前の御旅所まで祭り囃子と神輿が練り歩く。 |
|
 |
 |
| 蒸し暑い式場に清々しい神楽鈴と5色布 |
四基鎮座する神輿前で巫女の舞い奉納 |
|
寒川神社は、相模国一之宮と称され、千五百年余の歴史を有する神社で、
朝廷をはじめ源頼朝や北條義時そして武田信玄などの武将や多くの民間と、幅広く信仰を受けてきました。
関八州の裏鬼門に位置し、古くより八方除の守護神として信仰されています。 |
|
 |
|
四基の先駆けの宮山 寒川神社 神社名布を装着しない 「台座 四尺 昭和50年建造」 |
 |
 |
| 岡田 菅谷神社 「台座 四尺 天保年間建造」 |
倉見 倉見神社 「台座 不明 昭和54年建造」 |
 |
|
四本の警護提灯に囲まれて寒川町商工会の御旅所に入り込む先頭の寒川神社 |
 |
|
四基の殿の一番手前の一之宮 八幡大神が御旅所へ入り込む 「台座 不明 昭和60年建造」 |
|
御旅所: 寒川町商工会 高座郡寒川町宮山141-1 寒川神社の御旅所碑が立つ |
|
 |
 |
| 寒川神社神職の御旅所での神輿パレード祝詞 |
菅谷神社は担いで帰路へ八幡大神はトラックで撤収 |
| |
 |
|
寒川神社浜降り祭の宮入 |
 |
|
寒川神社の樹木生い茂る約1キロの長い参道を寒川神社と倉見神社が連なって三の鳥居へ |
浜降祭 湘南地方に本格的な夏の到来を告げる浜降祭が海の日(第三月曜日)に行われ、
寒川神社・鶴嶺八幡社を始め、寒川・茅ヶ崎両市町鎮座の34社、38基の華美絢爛な神輿が出輿する。
祭場には、暁の渚に旭日を浴びて乱舞する勇壮華麗な神輿を一目見ようと、10数万人の観衆の熱気で包まれます。
「ドッコィ、ドッコィ…」の掛声も勇ましく、海に入り禊(みそぎ)をする神輿に興奮も最高潮に達します。
昭和53年 神奈川県無形民俗文化財に指定。 |
|
 |
|
寒川神社参道の三の鳥居と太鼓橋前に到達して寒川は境内神門へ倉見神社は馬車道へと別れる |
 |
 |
| ここから単機で太鼓橋と明神鳥居(第三鳥居)から神門を目指す |
重層の神門前でハンドマイクに鼓舞され宮入ご挨拶の神輿揉み |
 |
 |
| 神事の為に女官を先頭に境内に静々と入り込む神職達 |
神職に続きドッコイ繰り返し境内中央から拝殿に進む宮神輿 |
寒川神社は寒川比古命と寒川比女命のニ柱の神を祀り、寒川大明神と奉称している。
寒川大明神は相模国を中心に広く関東地方を開拓して、
衣食住など人間生活の根源を開発指導せられた関東地方文化の生みの親神様として敬仰されている。 |
|
 |
|
拝殿前で早朝2時半の宮出しから最後の担ぎだとドッコイどっこいと神輿揉みを繰り返す |
 |
|
御魂返しの神事の為に重厚な拝殿へと入り込む宮神輿 |
浜降祭の起源由緒は、定かではありませんが、江戸時代の安永9年(1780)の古記録が寒川神社に残っています。
明治9年(1876)には「みそぎ」神事を浜降祭の名称に。
(1) 寒川神社と鶴嶺八幡社が、江戸時代にそれぞれに「みそぎ神事」を行っていた。
(2) 南湖浜が、寒川大神降臨の故地との伝承がある。
(3) 寒川神社の神輿が、天保年間の国府祭(現在も5月5日斎行)の帰路、相模川に流失し南湖の浜に打ち上げられ、
戻ってきた故事による。 |
|
|
yahoo!japan
登録サイト フリ-ソフトで作成のHP。 |
|